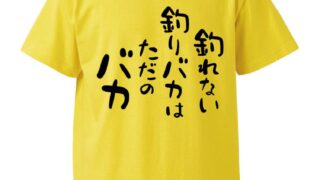ぶっこみサビキのデメリット

ぶっこみサビキのデメリットは、以下のようなものが挙げられます。
タナの調節ができない
ぶっこみサビキは、仕掛けを水中に沈めて釣るため、タナの調節ができません。そのため、底にいる魚しか狙えません。
活性が高い場合は表層や中層が良い場合もあるので、その日の状況でウキを付けると良いでしょう。
根掛かりしやすい
ぶっこみサビキは、仕掛けが底付近にあるため、根が多い場所では根掛かりしやすいです。根掛かりを防ぐためには、釣り場の地形や仕掛けの長さなどを考慮して、釣り方を工夫する必要があります。
根がきつい場所であれば仕掛けをあまり動かさないようにしたり、動かす場合は1号などの重さの軽い捨て錘を利用したほうが根掛かりしにくくなります。
捨て錘は針金や石を使う方法もあります。
コマセが必要なため手間がかかる
ぶっこみサビキは、魚を寄せるためにコマセが必要となります。コマセを撒くためのコマセカゴや、コマセを入れる容器など、道具を用意する必要があります。また、コマセを入れるのにも手間がかかります。
針にオキアミを付けると釣れますが、すぐに無くなるデメリットがあります。
長持ちするパワーイソメやガルプを針に付ける方法がおすすめです。
初心者にはアタリがわからない
ぶっこみサビキは、仕掛けの絡まりや、アタリがわからないなど、コツをつかむまでに時間がかかります。そのため、初心者には難しい釣り方と言えます。
根魚以外は遠くにラインが動くのでアタリが判りやすいですが、根魚は近くの根に潜るのでアタリが判りにくくなります。
糸ふけを取ってアタリを分かりやすくして、ラインの動きにも注意しましょう。
PEラインは少しでも弛むとアタリが判らなくなります。
置き竿にする場合はナイロンがアタリが判りやすくなります。
ぶっこみサビキで夜にアタリがわからないなら仕掛けにケミホタルを付ける方法もあります。
絡まる
魚が釣れたことに気が付かないで時間が経過すると仕掛けが絡まる可能性が高くなります。
また錘が軽くても絡まりやすくなります。魚のアタリには注意しましょう。
大物に釣り竿を持っていかれる
ウキサビキの場合はウキが先に沈むので釣れたことがわかりやすいですが、ぶっこみサビキはアタリに気付いた時には釣り竿ごと海にもっていかれる可能性が高くなります。
置き竿にする場合はロープで重い物に固定しておいた方が安心です。
ぶっこみサビキは、初心者でも簡単に始められる釣り方ですが、上記のようなデメリットがあることを理解しておくことが大切です。
ぶっこみサビキで釣れない原因
ぶっこみサビキで釣れない原因には、以下のような理由が考えられます。
- 仕掛けが適切でない
仕掛けが適切でないと、魚が食い込みにくくなります。仕掛けの種類やサイズ、色などを、釣りをする場所や魚のサイズに合わせて選ぶようにしましょう。
魚が小さいサイズの時は針も小さくすると釣れやすくなります。
- コマセが足りない
コマセが足りないと、魚を寄せにくくなります。コマセを撒きながら、仕掛けをシャクるようにしましょう。
- シャクるスピードが速すぎる
シャクるスピードが速すぎると、魚が追いつきにくくなります。ゆっくりとシャクるようにしましょう。
- アタリがわからない
アタリは糸を張ってわかるようにしましょう。
アタリがわからないと、魚がかかっているのもわからず、バレて釣れないです。アタリがわかりやすい仕掛けや、アタリを察知する感覚を身につけるようにしましょう。
夜はケミホタルを仕掛けに付けて確認する方法もあります。
- 魚がいない
魚がいない場所で釣りをしても、釣果は上がりません。魚の回遊ルートや餌場となるプランクトンの量などを考慮して、釣り場を選ぶようにしましょう。
ぶっこみサビキで釣果を上げるためには、上記の点を押さえることが大切です。
以下に、ぶっこみサビキで釣果を上げるコツをご紹介します。
- 仕掛けは、釣りをする場所や魚のサイズに合わせて選ぶ
- コマセは、こまめに撒きながらシャクる
- シャクるスピードは、ゆっくりめにする
- アタリがわかりやすい仕掛けを使う
- 魚の回遊ルートや餌場となるプランクトンの量などを考慮して、釣り場を選ぶ
これらのコツを押さえて、ぶっこみサビキで釣果アップを目指しましょう。
どうしても釣れない時はぶっこみサビキにアオイソメなどの餌を付ける
どうしても釣れない時はサビキに餌を付けるのがおすすめです。
オキアミ、アオイソメを付けると効果的です。
パワーイソメは生エサと違い保存が効くのでおすすめです。
ぶっこみサビキで夜にアタリがわからないなら仕掛けにケミホタル
ぶっこみサビキ釣りにおいて、ケミホタルは夜間の釣りにおける重要な役割を担います。ケミホタルを使用することで、夜間でも仕掛けを目立たせ、魚を引き寄せる効果が期待できます。ここでは、ケミホタルの使用方法や選び方についてご紹介します。
ケミホタルとは
ケミホタルとは、化学発光を利用した釣り用の光る小道具です。暗闇の中でも光り、魚の注意を引き、仕掛けやエサへの興味を促します。夜釣りにおいては、これが魚を寄せる重要なキーポイントとなります。
ケミホタルの役割
- 夜間の視認性向上: ケミホタルが発する光によって、暗闇でも仕掛けの位置を確認しやすくなります。これにより、釣り手が狙ったポイントに正確にテンションをかけることができます。
- 魚を引き寄せる: 特にアジやサバなど、視覚に頼って餌を探す魚種にとって、ケミホタルの光は魅力的に映ります。夜間における餌への関心を高めることができ、釣果の向上が期待できます。
ケミホタルの選び方と使用方法
- サイズ選び: ターゲットとする魚種によって、適切なケミホタルのサイズが異なります。アジやサバなどを狙う場合は、ある程度大きめのケミホタル(75mm以上)がおすすめです。
- 使用位置: ケミホタルは仕掛けの中に組み込むことで、最大の効果を発揮します。魚が餌に興味を持ちやすい位置、たとえばウキの下やサビキの間などに配置すると良いでしょう。
- 常夜灯付近での使用: 明るい場所では必ずしもケミホタルが必要とは限りませんが、暗い場所や夜間に常夜灯から離れたポイントで釣りをする際には、ケミホタルの使用が推奨されます。
夜間のぶっこみサビキ釣りで仕掛けにケミホタルを付けるとアタリが確認できるので、釣果を格段に向上させることができます。是非、試してみてくださいね!
ぶっこみサビキのメリット
ぶっこみサビキのメリットは、以下のようなものが挙げられます。
- 初心者でも簡単に始められる
ぶっこみサビキは、仕掛けを水面に投げ入れて、コマセを撒きながらシャクるだけで釣れるため、初心者でも簡単に始められます。
ウキを付けなくても良いので仕掛けを簡単に準備する事ができます。
- 釣果が上がりやすい
ぶっこみサビキは、コマセを使って魚を寄せることができるため、釣果が上がりやすいです。特に、アジやサバなどの回遊魚を狙うのに適しています。
- さまざまな魚が釣れる
ぶっこみサビキは、アジやサバなどの小型魚だけでなく、イワシやカマスなどの中型魚、メバルやカサゴなどの底物まで、時期を問わずさまざまな魚が釣れます。
- 夜釣りにも適している
ぶっこみサビキは、光に寄ってくる魚が多いため、夜釣りにも適しています。
- 冬の時期にもおすすめ
ぶっこみサビキは活性が低くて底にいる事が多い冬の時期にもおすすめです。
ぶっこみサビキは、初心者でも簡単に始められる、釣果が上がりやすい、さまざまな魚が釣れるなど、さまざまなメリットがあります。そのため、釣りを始めてみたい初心者や、手軽に釣りを楽しみたい人におすすめの釣り方と言えます。
ぶっこみサビキでサーフからの釣り
サーフでのぶっこみサビキ釣りは、特に大型の魚を狙う際に有効な方法です。この釣法では、通常のサビキ釣りで狙えない深場や沖のポイントを攻めることが可能になり、大型のアジなどを効率的に釣り上げることができます。
ぶっこみサビキの特徴
- フロートで直立: この釣法の特徴は、フロートによってサビキ仕掛けを底で直立させることができる点です。これにより、底付近を狙った釣りがしやすくなります。
- 遠投力: ぶっこみサビキは遠投性に優れており、通常のサビキでは届かない沖のポイントや深場も狙うことができます。これが、特にサーフでの釣りにおいて強力な武器となります。
サーフでの活躍
- 大型アジの狙いどころ: サーフでぶっこみサビキ釣りを行うと、30cm級の大型アジがヒットすることもあります。特に、沖合に深場が隣接したサーフでは、足元のサビキ釣りではなかなかお目にかかれないサイズに出会える可能性があります。
- 混雑時の強み: オモリが底に着いているため、仕掛けが流れにくく、混雑する釣り場でも少し沖合を狙いやすいです。フロートがついていると、小さい魚のアタリがわかりにくい可能性はありますが、全体として扱いやすい仕掛けです。
仕掛けの作り方&釣り方
- しもり浮きと下カゴ仕掛け: ぶっこみサビキはしもり浮きとカゴを使用します。しもり浮きが仕掛け全体を海底で立ち上がらせるので、重要な要素です。下カゴ仕掛けが一般的に使われ、遠投性や波や潮流の弱いエリアに適しています。
ぶっこみサビキでサーフからの釣りを試す場合は、フロートで仕掛けを直立させ、遠投性を活かして底付近や沖にいる大型の魚を狙ってみましょう。大型アジなどを狙うのに最適な時期や時間帯もありますので、朝夕のマズメ時に試すことをおすすめします。
サーフでのぶっこみサビキ釣りは、異なるサイズの魚を狙いたいときに挑戦すると新たな楽しみが見つかるかもしれませんね!
ぶっこみサビキの根掛かり
ぶっこみサビキは仕掛けが流されると根掛かりする可能性が高くなります。
流されないように重い錘を使うと良いでしょう。
サーフなどでも根が多い場所は釣れますが根掛かりが多くなります。その場合はぶっこみサビキではなくウキで底を狙った方が効率よく釣れます。
ぶっこみサビキで使用するオモリの重さ
ぶっこみサビキで使用するオモリの重さは、状況によって大きく変わります。
考慮すべき要素
- 釣り場
- 水深
- 潮の流れ
- 風力
- 仕掛け
- 仕掛けの長さ
- コマセカゴの重さ
- 狙う魚
- 魚の種類
- 魚の活性
目安
一般的な目安としては、以下の通りです。
- 浅場(水深1~2m)
- 5号~10号
- 中深場(水深5m)
- 10号~15号
- 深場(水深10m以上)
- 15号~20号
ただし、これはあくまで目安です。 上記で挙げた要素を考慮し、適切なオモリの重さを選ぶことが重要です。
選び方のポイント
- 軽めのオモリからスタート
- 軽めのオモリから始めて、必要に応じて重さを増やしていくのがおすすめです。
- 複数のオモリを用意しておく
- 状況に合わせて、複数のオモリを用意しておくと便利です。
- 竿のオモリ負荷を確認する
- 使用する竿のオモリ負荷を超えない範囲でオモリを選びましょう。
オモリの種類
ぶっこみサビキで使用されるオモリには、以下のような種類があります。
- 中通しオモリ
- 竿に通して使用するオモリです。
- ナス型オモリ
- 仕掛けに直接結びつけるオモリです。
- ジェット天秤
- 飛行距離を伸ばしたい場合に使用します。
冬のぶっこみサビキ釣り
冬のぶっこみサビキ釣りは、アジやカサゴなどの根魚を狙うのに最適な釣り方です。しかし、冬は水温が低く、魚の活性も低くなるため、釣果を出すためにはいくつかのポイントがあります。
少しでも水温が高い地域での釣りがおすすめです。
ぶっこみサビキで大アジを狙う
時期と場所
ぶっこみサビキで大アジを狙うのに最適な時期は、秋から冬にかけてです。この時期のアジは脂が乗っていて、とても美味しくなります。場所としては、サーフや磯がおすすめです。特に、潮通しの良い場所を選ぶことが重要です。
仕掛け
仕掛けは、市販のぶっこみサビキ仕掛けを使うことができます。しかし、大アジを狙う場合は、以下のような点に注意して仕掛けを自作することをおすすめします。
- ハリスは、8号~10号程度の太めのものを使用します。
- 針は、アジ針10号~12号程度のものを選びます。
ぶっこみサビキと投げサビキの違い
ぶっこみサビキと投げサビキは、どちらもサビキ仕掛けを使って魚を釣る方法ですが、いくつかの違いがあります。
仕掛け
ぶっこみサビキ
- ウキを使わず、オモリを重くして海底に沈めます。
- 仕掛けが長い(3~5m程度)。
- ハリスが太め(8号~10号程度)。
投げサビキ
- ウキを使って仕掛けを漂わせます。
- 仕掛けが短い(1.5~3m程度)。
- ハリスが細め(4号~6号程度)。
釣り方
ぶっこみサビキ
- 仕掛けを投入したら、竿を置き竿にしてアタリを待ちます。
- アタリがあったら、竿を大きく合わせます。
投げサビキ
- 仕掛けを投入したら、ウキの動きを見ながら魚を誘います。
- ウキが沈んだら、竿を少しだけシャクリ、その後ゆっくりと巻き上げます。
釣れる魚
ぶっこみサビキ
- アジ、カサゴ、メバル、アイナメなど
投げサビキ
- 小アジ、サバ、イワシなど
メリット・デメリット
ぶっこみサビキ
メリット
- ウキを使わないので、遠投しやすい。
- 根魚にも効果的。
デメリット
- アタリが出にくい。
- 仕掛けが絡みやすい。
投げサビキ
メリット
- ウキを使って魚の活性を把握しやすい。
- アタリが出やすい。
デメリット
- 遠投しにくい。
- 根掛かりしやすい。
まとめ
ぶっこみサビキと投げサビキは、それぞれ異なる特徴を持つ釣り方です。状況や狙う魚に合わせて、使い分けることが重要です。
以下は、それぞれの釣り方に適した状況の例です。
ぶっこみサビキ
- 深い場所や根が多い場所
- 風が強い日
- 根魚を狙いたいとき
投げサビキ
- 浅い場所
- 風が弱い日
- アジやサバなどの回遊魚を狙いたいとき
ぜひ、それぞれの釣り方を試してみて、自分に合った釣り方を見つけてください。
ぶっこみサビキとは
ぶっこみサビキとはサビキの上にフロートを付けて底でサビキを直立に立たせる仕掛けです。
フロートでサビキが浮くことで針が流される根掛かりが減ります。
ぶっこみサビキと投げサビキの違いは、ぶっこみサビキは投げて底で魚が掛かるのを待つ釣り方、投げサビキは回遊している魚を自分で探す釣り方です。
ぶっこみサビキの仕掛け
ぶっこみサビキの仕掛けは、以下の4つのパーツから構成されています。
- サビキ仕掛け
- コマセカゴ
- ウキ
- オモリ
それぞれのパーツの役割と選び方について、以下に説明します。
サビキ仕掛け
サビキ仕掛けは、ハリが6~7本付いた仕掛けが一般的です。ハリは、豆アジ狙いの場合は2~3号程度のサイズがおすすめです。大物狙いの場合は針を大きくします。また、ハリの色は、アジやサバなどの魚によく見られる銀色や黄色がおすすめです。
サビキ仕掛けには、以下のような種類があります。
コマセカゴ
コマセカゴは、コマセを撒くためのものです。コマセカゴは、プラスチック製や金属製など、さまざまな種類があります。また、コマセカゴのサイズは、釣りをする場所や魚のサイズに合わせて選びましょう。
フロート
サビキの仕掛けを直立に立たせるためのウキです。
オモリ
オモリは、仕掛けを沈めるためのものです。オモリは、遠投する場合の重さは10号程度がおすすめです。また、オモリは、形状は、丸型やカタカナ型など、さまざまな種類があります。
ぶっこみサビキの仕掛けを選ぶ際には、以下のポイントを押さえましょう。
- 釣りをする場所や魚のサイズに合わせて選ぶ
釣りをする場所や魚のサイズに合わせて、仕掛けを選ぶことで、釣果を上げることができます。
- 光る仕掛けを使う
夜釣りでは、光に寄ってくる魚が多いため、光る仕掛けを使うと、釣果が上がりやすくなります。
- 絡みにくい仕掛けを選ぶ
夜釣りでは、仕掛けが絡みやすいため、絡みにくい仕掛けを選ぶと、釣りがしやすくなります。
ぶっこみサビキの仕掛けは、釣り具店で購入することができます。また、インターネットでも購入することができます。
ぶっこみサビキで遠投するならPEラインがおすすめ
ぶっこみサビキで遠投するならPEラインがおすすめです。
PEラインは細くて強度もあり、たるみが無ければ感度も高いので遠くの魚の群れを狙い撃ちする事ができます。
ただしPEラインは慣れるまで扱いが難しく、直接仕掛けに結ぶと強度も下がるのでリーダーを付けないといけないなどデメリットもあります。
青物が回遊している時はメタルジグを付けると釣れる可能性が上がる
大きい青物が回遊している時はぶっこみサビキの錘の代わりにメタルジグを付けると釣れる可能性が高くなります。
ただし底を取りすぎると根掛かりの確率も高くなってしまうので、根がひどい場所では底になるべく落とさないように注意しましょう。
ぶっこみサビキ釣りの基本
準備
道具
- 磯竿または投げ竿(長さ3~4m程度)
- スピニングリール(2500~4000番程度)
- 道糸(3~4号ナイロンライン)
- ぶっこみサビキ仕掛け
- コマセ(アミエビ、オキアミ、イワシミンチなど)
- コマセカゴ
- バケツ
場所
- 港湾、磯、サーフなど
- 潮通しの良い場所
釣り方
- コマセの準備
- コマセを混ぜ、コマセカゴに詰めます。
- 仕掛けの準備
- ハリスに針を結び、サビキ仕掛けにセットします。
- 道糸にコマセカゴと仕掛けを結びます。
- 仕掛けの投入
- 振りかぶって仕掛けを遠投します。
- アタリの待ち
- 竿を置き竿にしてアタリを待ちます。
- アタリ
- アタリがあったら、竿を大きく合わせます。
- 魚とのやり取り
- 魚を釣り上げたら、針を外してバケツに活かしておきます。
コツ
- コマセは新鮮なものを使用しましょう。
- 仕掛けを投入する前に、コマセを撒いて魚を寄せておくと効果的です。
- アタリがあったら、すぐに合わせないようにしましょう。
- 魚を釣り上げたら、すぐに針を外してバケツに活かしておきましょう。
その他
- 仕掛けは市販のものを使用できますが、より効果的に釣果を出すためには、自分で作るのもおすすめです。
- 冬のぶっこみサビキ釣りでは、仕掛けや釣り方に工夫が必要です。
- 安全に釣りを楽しむために、ライフジャケットなどの装備を着用しましょう。
釣りをする場合はライフジャケットをしよう
釣りをする場合はライフジャケットをしましょう。
海に落ちた場合は上がれない場所が多く、泳げる人でも救助が来る迄体力が持ちません。
ライフジャケットを付けない場合は生存率がかなり低くなります。
必ずライフジャケットは装着しましょう。