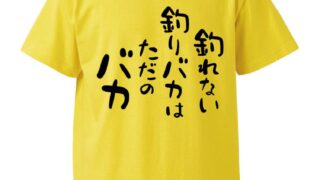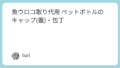「魚のウロコ取り」って、家でやるとキッチンがウロコまみれになりがちですよね…。
でも、工夫次第でほとんど飛び散らずに取る方法があります。
以下に「飛び散らないウロコ取り法」と「おすすめ道具」を紹介します👇
🧽 飛び散らないウロコ取り方法
①鱗トル
飛び散らず簡単にザーッとうろこを取ることができる商品です。
値段は高いですが、何度も魚を捌く事がある人は買っても損しないと思います。
リンク
100均のウロコ取り 飛び散らない方法
ダイソー・セリア・キャンドゥなどの100均のうろこ取りは手軽で便利ですが、構造上の限界から飛び散りやすいのは仕方ない部分もあります。
① 袋 or ビニール内ウロコ取り法
- 魚をポリ袋やジップロックに入れたままウロコ取りでこする。
- ウロコは袋の中に全部閉じ込められるので100%飛び散らない!
✅コツ
- 袋は少し大きめに(魚の倍くらい)
- 中に少し水を入れておくとウロコが浮いて取りやすい
② 新聞紙+濡れ布法
- 魚の下に新聞紙を敷き、濡れ布巾やキッチンペーパーをかぶせてからウロコ取り。
- 飛び散る前に布がキャッチしてくれます。
✅おすすめ:台所で小魚を処理するとき。
③ 水中ウロコ取り
- 水を張ったボウルやシンクの中でウロコを取る方法。
- 水がウロコを押さえつけるので飛び散りゼロ。
✅注意点:水が冷たい時はゴム手袋必須。
✅中型魚まで対応(アジ、メバル、キス、カワハギなど)
④ ペットボトル半割り法(即席カバー)
- 500mlペットボトルを縦に半分切り、魚の上にかぶせてウロコを取る。
- カバーが飛び散りを防止。
✅見た目は少し不格好ですが、屋外やキャンプ釣りでは最強。
⑤ 外でやる+新聞紙トレー
- 庭・ベランダ・釣り場などで新聞紙の上に魚を置き、作業後はそのまま包んでポイ。
- 飛び散っても気にならない&掃除ラク。
🔧 飛び散らないおすすめウロコ取りグッズ
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| 「パール金属 ウロコ取り(カバー付き)」 | 透明カバーで飛び散り防止。家庭用に人気。 |
| 「シマノ うろこ取り一刀両断」 | ステンレス刃+飛び散りガード付き。魚を傷めにくい。 |
| 「魚っ平(うおっぺい)」 | 柔らかいゴム素材でウロコを優しくこそげ取る。 |
🧼 後片付けのコツ
- 新聞紙+ラップの上で作業すれば、そのまま包んで捨てられる。
- 流しの排水口にストッキングネットをつけておくと、ウロコが詰まり防止に。
鯛鱗取り方熱湯
実は「熱湯を使った鯛(タイ)のウロコ取り」は、
プロの料理人や釣り人も使う裏ワザ的な方法です。
正しくやれば、ウロコが一瞬で浮いて、飛び散らずにツルッと取れるんです。
🔥 鯛のウロコ取り「熱湯法」手順
🐟 用意するもの
- 鯛(ウロコ付きのまま)
- 熱湯(90〜95℃)
- ボウル or バット
- 氷水(締め用)
- トング or さいばし
✅ 手順
- 鯛を洗って水気をふく
- 表面のヌメリや汚れを軽く落とす。
- 熱湯をかける(短時間!)
- 90〜95℃のお湯を全体にサッと5秒ほどかけます。
- この時、ウロコが「フワッ」と浮き上がるように白っぽくなる。
- 熱湯を長時間かけすぎると皮が破れるので注意。
- すぐに氷水に入れる
- 皮の縮みを止めて、身の火通りを防ぐ。
- 包丁の背やウロコ取りでなでる
- ウロコがスルッと滑るように取れる。
- ほとんど飛び散らず、キッチンが汚れない。
🧠 ポイント
- 熱湯でウロコと皮の間のコラーゲン層が緩むため、簡単に剥がれる。
- 大鯛の硬いウロコも、力を入れずにサラッと落ちる。
- 飛び散り防止効果が高く、後片付けがラク。
⚠ 注意点
- 熱湯をかけすぎると皮が破れたり、身に火が通る。
- 刺身用など生食する場合は避けたほうが無難。
→ 表面に火が通ると身質が変わるため。 - 加熱調理(塩焼き・煮つけ・鯛めしなど)向け。
🍽 向いている調理
- 塩焼き
- 煮つけ
- 鯛めし
- アラ炊き
💡プロっぽい一工夫
ウロコを取ったあとに塩を軽くふって再度湯引きすると、
ぬめりと臭みが完全に消えて、皮がパリッと焼けます🔥